ジェネリックメーカーの規模を世界と比較すると日本はひとたまりもない
更新日:
新薬メーカーが目指す最大収益化とは
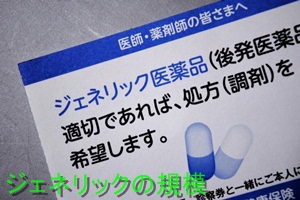 市場は国際化に突っ走り、それはすなわち欧米並みに新薬とジェネリックの入れ替わりを推進するベクトルがあります。
市場は国際化に突っ走り、それはすなわち欧米並みに新薬とジェネリックの入れ替わりを推進するベクトルがあります。これに対応するには特許切れの新薬にしがみつかず、ジェネリックでも儲ける、という大収益化を基準にした戦略が必要になってくる。
自らが持つ特許切れの新薬の薬価がどのくらいのペースで下がるか。
あるいは他社のジェネリックがどのくらいの数量出てくるか。
自らが扱うとどのくらいの転換が進むか。その場合、どう配分したら利益が最大になるか。
そうしたあらゆる要因を見極めて、自らが積極的にあるいはバランスを取ってジェネリックを扱う戦略が求められ、その機動的な戦略のために、ノバルティスのようにグループでジェネリックを扱う別働隊が必要とされる。
日本ではエーザイがエルメッドエーザイというジェネリック専用の別会社を持っているが、活動そのものは活発とは言い難い。
国内外資とも多くの新薬メーカーは別働隊を持たない、すなわち、そのために既存のジェネリックメーカーを買収するという可能性があるわけだ。
世界と日本のジェネリックメーカーの格差
世界のジェネリックメーカーの推定売り上げは、
①テバ(イスラエル)8400億円
②サンド(スイス)7200億円
③マイラン(米国)5000億円
④ バール(米国)3000億円
⑤ラシオファルム(ドイツ)2800億円
⑥アクタビス(アイスランド)2200億円
⑦ワトソン(米国)2000億円
⑧ランバクシー(インド) 1600億円
⑨ スタダ(ドイツ) 1500億円
⑩ガーディオン・リッチャー(ハンガリー) 1300億円(06年度推定)
聞いたことのない会社ばかりだろうが、マスコミにとっても新薬ではないだけに話題性に乏しく、取り上げる機会が少ない。ジェネリックをおとしめるつもりはないが、これは2番手商品を扱うものの宿命なのだ。
いずれにせよ、世界規模で活躍する医薬品メーカーとしての陣容は整っている。ジェネリックは医薬品の特性より、価格が決め手になるだけに、企業体力こそが生き残りの鍵。
体力のある会社のジェネリックがより安く提供でき、より多く販売できる。日本的な情実の入る余地はない。冷徹な資本の論理に貫かれている。
その巨大なジェネリックメーカーが狙う日本のジェネリック業界は実にお寒い限り。大手といわれる4社の売り上げ数字を比較すれば、何も語らなくてもわかるはず。
沢井製薬、343億円
東和薬品、292億円
日医工、293億円
大洋薬品工業、343億円
前2社は上場企業だ。もし外資が本気で日本のジェネリックに取り組むなら、これらの国内大手はひとたまりもない。
真っ正面から価格競争になるにしても、M&Aになるにしても、国内大手は守り一辺倒にならざるを得ないだろう。
実際、水面下では様々な組み合わせでのM&A交渉が進められているといわれ、新薬市場よりはるかに急速に再編が進むことは必至。それを先取ったのが、インドメーカーによる共和薬品や日本ユニバーサル薬品の買収といえる。
この記事を見た人は、下記にも注目しています!
- ジェネリック市場が薬や医療品の未来を担っているが日本は未発達
- 世界の医薬品メーカーにとってシェア第2位を誇る日本市場は重要
- くすりに関する薬用語一覧&解説つき
- 医薬品・薬の一覧表|病名や治療効果からみた薬リスト
